
「内製化を柔軟に進行出来ているワケ」朝日新聞社×レバテック
(本記事は朝日新聞テックフェス2024のテクノロジーショーケース第2部の採録です。当日の様子はこちら↓からご覧いただけます)

レバテック・髙橋氏(以下、敬称略):
レバテック株式会社で代表執行役社長をしております髙橋と申します。弊社は、エンジニアやクリエイターと企業をマッチングする事業をしております。中途領域、フリーランス、新卒領域でも事業展開をしております。年間1万回ぐらい企業に訪問していく中で、働く環境や使っている技術をリサーチしています。エンジニアやクリエイターの方はそのような条件を気にされることが多いので、企業訪問から得た情報を提供させていただき、マッチングにつなげていきます。今は年間約40万人の方々にご登録頂いてるサービスです。
朝日新聞社・都田:
40万人も登録されているんですね。どのように集められたんですか。

髙橋:
主に広告ですが、実はフリーランスの事業を18年ほどやっていまして、だいぶ初期からやっているので、これまでの積み重ねでご登録いただいているという状況です。

都田:
私も簡単に自己紹介させていただきます。朝日新聞社CTO室の室長補佐をしています都田と申します。このフェスもCTO室主催です。皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。室長に代わりまして御礼申し上げます。私は2019年から今年3月まで朝日新聞デジタルの開発を担当していました。4月からCTO室で主にキャリア採用を担当しています。今日は内製化について、レバテックさんに色々とご協力いただきながらお話していきたいと思います。
髙橋:
もう(朝日新聞社とは)3~4年のお付き合いですが、大企業で内製化に困っていらっしゃる企業様は多いです。私も大企業の役員の方からご相談を頂くケースが多いです。やはり一歩目を踏み出すのが難しいとか、ITベンダーに開発をお願いしていて受発注の関係から抜け出せない、ということに悩んでいらっしゃる企業が多いと思っています。改めて、御社はどういった目的で内製化を進められたのでしょうか。
都田:
当時、朝日新聞デジタルの担当をしていて、それまでは今おっしゃったように、外部の企業さんに開発をお願いしていましたが、改善のスピードや、品質を社員でコントロールしにくいという点で課題がありました。まずは小さく始めようということで、包から朝日新聞デジタルのリニューアルの話がありましたが、今のアプリのベースとなるリニューアルの際に、一部内製化を始めました。そこから少しずつ範囲を広げていっています。
髙橋:
3~4年前から支援させていただいていて、正直、内製化のお手本になるような事例であると思っています。ここまでエンジニア組織がどんどん大きくなるのも珍しいケースであると感じていました。一つリニューアルを小さく始めてみて、そこから徐々に大きくしていくというところも理想的だと思います。その中で組織拡大で悩まれてる企業さんは多いと思うのですが、内製化のところで3~4歩先に行かれている御社は今どういった体制で開発されていますか。
都田:
3~4歩先はちょっと言い過ぎだと思いますが…他社さんをいろいろと参考にさせていただきながらやってきました。組織でいうと、それまではエンジニア部門と事業部門があって、事業やサービスの開発をエンジニア部門にお願いするかたちでした。そうするとスピード感のある開発ができなかったり、コミュニケーションにちょっとした壁があって受発注関係になりやすかったり、と課題がありました。そこでエンジニア数名に、プロダクトと一緒に事業部門に異動していただくところから始めました。そこから、事業部門の人たちとエンジニアのコミュニケーションは活発になったと思います。
髙橋:
なるべく内製化して、よく「手の内化」と表現されますが、そのために内製化のエンジニアを雇ったとしても、結局社内で受発注の関係になってしまうという事例はよくあると思っています。そこから事業部門に広げるというのは、ハードルが高い印象もありまして、事業部門の人がなかなかITのことを理解してくれない、どうエンジニアとコミュニケーションを取っていいかわからない、ということがあると思います。そこはどう解消されたのでしょうか。
都田:
やはり異動したことでコミュニケーションが増えますので、その辺りは徐々に解消していったのではないでしょうか。特効薬は無いと思います。弊社はもともとそこまで壁があったわけではないので、徐々に打ち解けていったと思います。
髙橋:
最近、大企業の内製化や、ガブテック(GovTech)という言葉がよく出てきますが、政府系のITで働きたいという方も非常に増えてきた印象です。我々もそこへの支援をさせていただいています。私はこれは対照的な流れだと感じていて、ひとつが旧来ある政府や大企業をDXしていくという文脈、もうひとつがITジェネラルな企業を大きくしていく、そこで開発をしていくという流れがあると思います。そこで、やりがいを改めて聞きたいと思います。
例えば、ITジェネラルな企業で働くほうが開発する環境が良いことが多いと思います。一方でDXとか内製化のほうが、より大きなものを変えられるというところが大きいです。あまり上手くいっていないところを大きくレバレッジをかけて事業展開できる、ということに喜びを感じる方も多いと思いますが、御社のエンジニアは、どういうことをモチベーションにされているのでしょうか。
都田:
IT企業と比較すると、環境が追いついていないからこそ、技術選定などエンジニアに裁量があって、自分たちで決められることが多いというところがあると思います。
髙橋:
大企業でITジェネラルではないからこそ、現場のエンジニアがITを選択できるというメリットがあるということですね。実際、弊社で支援させていただいているフリーランスで、御社のプロジェクトに入っている方からは、「自分の発言からツールの選定が行われた」「ITの大きなアーキテクチャの部分を提案させていただき、それが採択された」と聞いています。非常にやりがいがあると聞いています。
皆さんの意見を聞いて意思決定していくという文化があるのでしょうか。
都田:
私も実はそこまで技術的な部分に強いわけではないので、(社外CTOの)広木さんに来ていただいて組織や環境のことを相談し、御社をはじめパートナーさんを紹介いただきました。御社から優秀なエンジニアをご紹介頂いて、弊社の社員と一緒に働き、教育もしていただきながら少しずつ進めてきました。社員だけではエンジニアが足りない状況もあったので、二人三脚でやってきました。
髙橋:
やはり広木さんのような社外CTOがいらっしゃるというのは、非常に心強い会社だと思います。普段から社外CTOと技術のことを話しながら考えて進められているんですか。
都田:
そうですね。レビューをいただきながら進めています。
髙橋:
内製化の別の問題として、プロダクトではなく、社内の業務フローをより生産的にしていくとか、効率化していくことを求められることもあると思いますが、そのあたりもやっていますか。
都田:
そのあたりもエンジニアが中心となって取り組んでいます。御社からのフリーランスの方や、キャリア採用にも力を入れており優秀なエンジニアが少しずつ入ってきていまして、最初に内製化を始めた時と比べると徐々にではありますが、主体的に取り組んでくれています。
髙橋:
本当にエンジニアの裁量が大きくて、現場や業務フローに入り込んで話を聞いて開発できるのは素敵だと思います。私たちも日々エンジニアの方々とお話させていただく中で、職探しにおいてどれぐらいエンジニアやクリエイターが主体性をもって働けるのかは、大きなポイントだと感じています。企業によってはトップダウンで降りてきてエンジニアの中で意思決定ができない、経営者の意向が強くてその通りに仕様を作らないといけない、ということがあると思います。ボトムアップができていること自体がすごいなと思いますが、これは御社のカルチャーが大きいのでしょうか。
都田:
大きいと思います。特に技術的なところで言うと、トップダウンというのはあまりないと思います。
髙橋:
今後このような内製化の体制や、それ以上にこういう課題を解決していこう、と考えていることはありますか。
都田:
やはりエンジニアの採用です。そこに課題があると感じています。御社には非常にご協力いただいていますが、もっと社員の比率を上げていきたいと考えています。
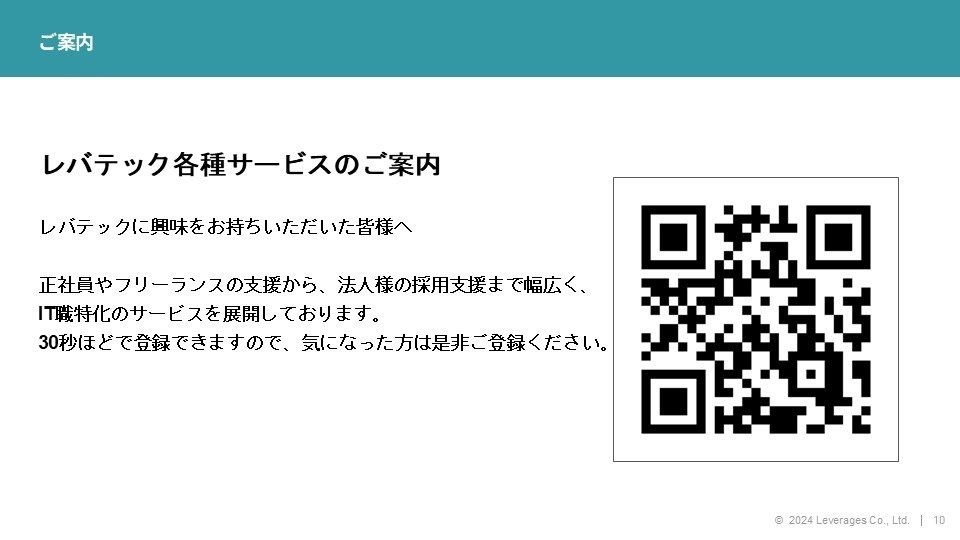
髙橋:
弊社も正社員やフリーランスの支援をさせていただいていますし、求職者の方にもご登録いただければ支援をさせていただきます。もし興味がありましたら、こちらのURLからご登録いただければと思いますので、よろしくお願いします。
都田:
弊社もキャリア採用を大々的に募集しておりますので、ぜひ宜しくお願いします。
・朝日新聞社(ITエンジニア)の求人一覧
https://techlife.asahi.com/jobs

